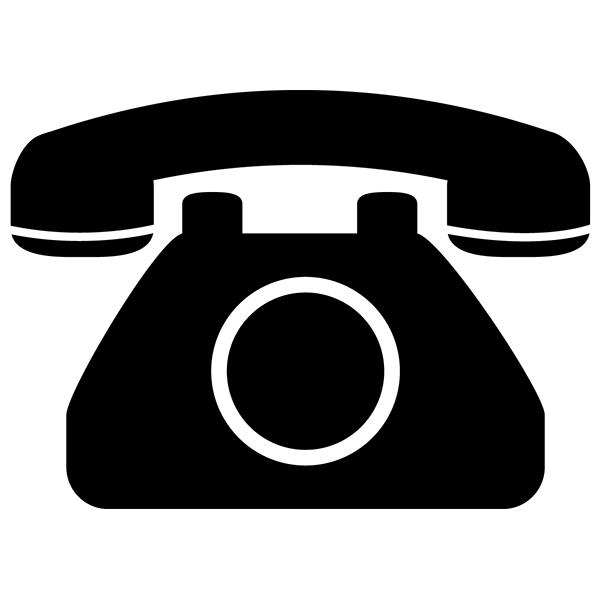仲介手数料2%・スピード重視の売却支援・スタッフも不動産オーナー



下記の物件を仲介手数料2%でご案内します
(例:1億円で売買が成約した場合、
他社であれば306万円+消費税(10,000万円×3%+6万円)となるところ
当社であれば206万円+消費税(10,000万円×2%+6万円)とお得です。)
他社であれば306万円+消費税(10,000万円×3%+6万円)となるところ
当社であれば206万円+消費税(10,000万円×2%+6万円)とお得です。)
※400万円以下は法律上の上限に従い承ります
1月25日日報 「絶景」がないなら作ればいい。逆境のリノベーション論
本日は、箱根エリアにある「立地は良いが、眺望に恵まれない」既存物件の再生計画を練りました。 リゾート開発において「眺望」は重要ですが、それが全てではありません。 窓からの景色が望めないなら、内装や中庭に圧倒的な世界観(アイコン)を作り込み、そこにいること自体を体験価値に変えればいい。
現在進行中のプロジェクトでは、元保養所の無機質な空間を、現代的なデザインとサウナ・温泉体験を融合させた「没入型施設」へと転換するプランを検討しています。 AIを活用して世界中の成功事例(眺望に頼らない人気ホテル)を分析し、そのエッセンスを日本の文脈に落とし込んでいます。
古い建物を取り壊すのではなく、知恵とデザインで新しい命を吹き込む。 この「再生のプロセス」こそが、高騰する建築コストへの対抗策であり、高収益を生む鍵です
1月24日日報 「待ち」の不動産屋からの脱却。仕入れの自動化戦略
本日は、当社の核心的な競争力である「仕入れ(ソーシング)」の強化に向けたシステム構築に時間を割きました。 一般的に不動産情報はレインズやポータルサイトで探すものと思われがちですが、本当に利益の出る案件は、市場に出回る前の「川上」に存在します。
私たちは現在、登記情報や独自のデータベースをAIで解析し、売却ニーズが発生する予兆を捉え、ダイレクトにアプローチする「源泉営業システム」を開発・運用しています。 本日はその精度を高めるため、ターゲット選定のアルゴリズムを見直しました。
「良い物件がない」と嘆くのではなく、「良い物件になる前の原石」を自ら掘り起こす。 この能動的な仕入れスタイルこそが、市況に左右されず安定した収益を生み出す基盤となっています。 テクノロジーで効率化し、最後は人と人との信頼関係でクロージングする。これが日本不動産の流儀です。
1月23日日報 100億円企業を作るための「因数分解」
日曜日の本日は、中長期的な経営計画のブラッシュアップに充てました。 具体的には、国内外の成功したホテル運営会社や不動産ファンドが、成長期に「どのような資本政策」と「運営戦略」をとっていたのかを徹底的に分析しました。
AIを活用して膨大なIR資料や過去のレポートを読み解くと、成功企業の背後には必ず、緻密に計算された「金融のロジック」と、顧客を惹きつける「独自のオペレーション」の両輪が存在することが分かります。 当社が目指す「GP(ゼネラル・パートナー)型デベロッパー」としての在り方も、これら先人たちの知恵を現代版にアップデートしたものです。
「午前勤務で年収1000万」という個人の目標を超え、組織としてどう社会にインパクトを与え、資産を築いていくか。 視座を高く持ち、思考のアクセルを踏み込んだ一日でした。 明日からの実務に、この戦略を落とし込んでいきます。
1月21日日報「想定外」をゼロにする。AI法務参謀との対話
本日は終日、進行中の宿泊プロジェクトにおける法務リスクの洗い出しを行いました。 旅館業法や民泊新法の規制動向、契約書における細かな条文解釈。 これらは事業の根幹に関わる重要な要素ですが、専門家任せにせず、経営者自身が「構造」を理解しておく必要があります。
私は現在、膨大な判例や法規制データを学習させたAIを「法務参謀」として活用し、あらゆるトラブルのシミュレーションを行っています。 「もしこうなったらどうするか?」という問いを何重にも重ね、論理的な抜け漏れを徹底的に塞ぐ。 この地味で緻密な作業があるからこそ、金融機関様やオーナー様に自信を持って事業計画を提案できます。
「神は細部に宿る」と言いますが、不動産事業において「細部」は「利益と信用」そのものです。 盤石な土台の上で、大胆な挑戦を続けていきます。
1月20日日報 「紙の図面」を待つ時間を、経営のスピードに変える
本日は、箱根エリアで計画中の新規宿泊施設のコンセプト設計に没頭しました。 通常、設計事務所に依頼して数週間かかる「外観パース」や「平面図」の作成ですが、当社ではAI画像生成技術と建築知識を掛け合わせ、会議中にその場で視覚化しています。
「こんなイメージ」と口頭で伝えるのと、その場で「このデザインですか?」と画像で見せるのとでは、合意形成のスピードが段違いです。 古い青焼き図面をデジタル化し、現代風のリノベーション案を即座にシミュレーションする。 このプロセスにより、投資判断までのリードタイムを劇的に短縮しています。
テクノロジーは、単なる効率化ツールではありません。 私たちのような少人数のデベロッパーが、大手に負けないスピードで「尖った企画」を生み出すための最強の武器です。 今年の箱根は、面白いことになります。
1月19日日報 「気合い」を「アルゴリズム」に置き換える
本日は午後から、進行中のリノベーション案件の進捗確認に着手。 現場から届いた見積もり査定を即座にリモートチームへ連携し、発注の意思決定を行いました。 物理的な距離があっても、クラウドとチーム連携で「判断のスピード」を落とさない。このスピード感こそが、再生事業における利益の源泉であり、リスク管理そのものです。
夜は、現在開発を進めている「源泉営業自動化ツール」について、AIパートナー(Gemini)と集中的なディスカッションを実施。 市場に出回らない「川上情報」を、いかに属人性を排して取得するか。 単なるリスト作成に留まらず、当社の投資基準に合致する「成約確度の高い案件」のみを自動抽出するロジックを構築しています。
「汗をかく」ことの尊さは否定しませんが、経営者の真の仕事は「汗をかかなくて済む仕組み」を作ることに汗をかく。 このシステムは、2026年の当社を支える強力なエンジンとなるでしょう。 明日も、圧倒的な生産性で市場をリードしていきます。
1月11日日報「特徴がない」という最強の武器。ヒルトン・マリオットに学ぶ “引き算” の開発戦略
今日は、次期開発案件に向けた市場調査(リサーチ)に時間を割きました。 テーマは、ヒルトン傘下の「Hampton Inn」やマリオットの「Fairfield」などが世界中で急拡大している「セレクトサービスホテル(宿泊特化型)」の分析です。
1. 「個性」のインフレに対する逆張り 日本の観光地では今、グランピングやコンセプチュアルな高級ヴィラなど、「個性的であること」がインフレを起こしています。しかし、AIを用いてグローバル市場の動向と顧客心理を深掘りすると、面白い事実が浮かび上がってきました。
多くの旅行者は、「宿そのもの」よりも「現地の食事や体験」にお金を使いたいと考えています。彼らが求めているのは、過剰なサービスや難解なコンセプトではなく、「裏切られない清潔さ」と「快適な睡眠環境」だけです。
2. 「Not Identity」という戦略 私はこれを「Not Identity(非・個性)」戦略と呼んでいます。 周囲が個性を競い合う中で、あえて「特徴を消す(標準化する)」ことは、オペレーションコストを劇的に下げ、利益率(GOP)を高めることに直結します。 金融機関の視点で見ても、流行り廃りの激しい「尖ったコンセプト」より、不況に強く需要が底堅いこのモデルの方が、ファイナンスの評価は高くなります。
3. AIで「巨人の肩」に乗る 今日の調査では、AI(Deep Research)を活用し、海外大手の収益構造や成長曲線を徹底的に洗い出しました。少人数のチームですが、情報量と戦略の解像度では大手に引けを取りません。 「面白みがない」と言われるかもしれませんが、「面白み(利益)」は決算書の中にこそあるべきだと私は考えています。
次の一手は、この堅実なモデルを日本の地方にどうフィットさせるか。静かに、しかし着実に準備を進めています。
1月10日日報 「たかがシーツ、されどシーツ」――6回転か10回転か、現場の数字に宿る経営哲学
昨日は、30年前のバブル経済と世界金融市場という、極めて「マクロ」な視点で思考を巡らせていました。 打って変わって、本日の私の脳内を占拠していたのは、極めて「ミクロ」な問題です。
それは、**「宿泊施設の枕カバーとシーツの在庫を、何セット持つべきか」**という一点です。
運営中のある施設において、リネン(シーツ類)の在庫基準を見直していました。 教科書的な運営理論で言えば、実際に使用する枚数の3倍〜5倍(3〜5回転)程度あれば、クリーニングのサイクルは回ります。現状、私たちは「6回転」分の在庫を持っており、理論上は十分すぎる数字です。
しかし、現場は理論通りには動きません。 突発的な連泊、予想外の汚損、クリーニング配送の遅延リスク。 「理論上は足りる」という状態は、裏を返せば「何かが一つ狂えばアウト」という綱渡りの状態でもあります。
私は本日、これを「10回転」まで引き上げる決断をしました。
一見すると、過剰在庫であり、無駄なコストに見えるかもしれません。 しかし、たかがシーツ1枚の不足で、大切なお客様の宿泊体験を損なうことこそが、我々にとって最大のリスクであり、ブランド毀損です。
これは、会社の財務戦略にも通じる話です。 ギリギリの資金繰りで効率を最大化するのではなく、不測の事態が起きてもびくともしない「十分な手元流動性(バッファ)」を確保しておくこと。 シーツの枚数も、キャッシュフローも、本質的な「安全マージン」の考え方は同じです。
『神は細部に宿る(God is in the details)』
数億円の不動産取引も、数百円の枕カバーの管理も、その根底にあるのは「お客様に対する責任」と「不確実性への備え」です。 現場の小さな綻びを見逃さない「虫の目」を持ち続けること。これも業務を遂行する上で欠かせない能力だと考えています。
細部へのこだわりを積み重ね、信頼という強固な地盤を築いてまいります。
1月9日日報 「歴史は繰り返さないが、韻を踏む」――1990年代のデータから読み解く、2026年の勝機
今日は一日、外出を控えてデスクに張り付き、ひたすら「過去」と向き合う時間を作りました。
具体的に何をしていたかというと、1980年代後半から1990年代初頭にかけての日本の不動産・金融市場のデータと、ここ数年の欧米における高金利下の不動産市場(特にマルチファミリー投資)の比較分析です。
なぜ、今さら30年以上前のバブル崩壊期のデータを掘り返すのか? そう不思議に思う方もいるかもしれません。
しかし、マーク・トウェインが残したとされる**「歴史は繰り返さないが、韻を踏む」**という言葉の通り、市場には時代を超えて共通する「構造的な歪み」が発生する瞬間があります。
融資が過熱する局面、金利が上昇に転じる局面、そして市場が調整される局面。 それぞれのフェーズで、どのようなプレイヤーが退場し、逆にどのような戦略を持っていた者が生き残ったのか。当時の「住専」や「ノンバンク」の動きと、現在のグローバルな資金の流れを重ね合わせることで、驚くほど多くのヒント(韻)が見えてきます。
私たち日本不動産株式会社が掲げる**『Special Ops unit(特殊部隊)』**というアイデンティティは、単に「難しい物件を扱う」という意味だけではありません。 多くの人が雰囲気に流されて投資判断をしてしまうような場面でこそ、こうした冷徹なデータ分析に基づき、誰も気づいていない「勝機」や、逆に見落とされている「リスク」を特定する情報戦の能力を指しています。
銀行様から大切なお金をお預かりして事業を行う以上、 「なんとなく儲かりそうだから」 という感覚的な経営は許されません。
過去の破綻事例を直視し、最悪のシナリオを想定した上で、それでもなお利益が出せる盤石なロジックを組み上げる。 地味で根気のいる作業ですが、この「臆病なまでのリサーチ」こそが、ここぞという時の「大胆な意思決定」を支える唯一の根拠になると私は信じています。
歴史から学び、未来の「住」と「旅」のあり方を再定義する。 2026年も、足元の数字とマクロな視点の両輪で、堅実に前へ進んでまいります。
11月26日 日報 民泊は「不労所得」ではない。世界データが示す現実と、私たちが目指す次のステージ。
民泊で楽に稼ぐ」の終焉。世界1,400人のデータから見えた、勝ち残るための「仕組み」とは。
PriceLabs社が発表した最新の「Global Host Report 2025」に目を通しました。世界中の民泊ホスト1,400名以上の生の声を集めた、非常に示唆に富むレポートです。
このデータを読み解くと、私たちが現在取り組んでいる事業の方向性――「個人の労働力に頼らない仕組み作り」の重要性が痛いほど分かります。
自戒も込めて、市場のリアルな現状を共有します。
1. 「副業」ではなく「第二の激務」 「民泊=不労所得」というイメージはいまだにありますが、現実は甘くありません。 回答者の83%が他の仕事を持ちながら運営しており、その多くにとって民泊は「片手間の副業」ではなく、本業が終わった後に始まる「第二の勤務(Second Shift)」になっています。
2. 多くのホストが「作業」に忙殺されている 時間が奪われている業務の上位は「管理業務(税務・会計など)」が76%、「物件の清掃・修繕」が72%でした。 本来、オーナーがやるべきは「戦略」や「投資判断」はずですが、現実は清掃手配やゲスト対応、帳簿付けといった「現場作業」にリソースを食い潰されています。
3. AI活用はまだ「発展途上」 興味深いのがテクノロジーへの姿勢です。**43%のホストがAIなどの新技術に「圧倒されている(Overwhelmed)」**と感じており、使いこなせていません。 AIを導入している層としていない層で、今のところ労働時間に大差がないというデータもあり、多くの人が「ツールに使われている」状態であることが伺えます。
— 私たちの現在地と、これから —
このレポートを読んで、改めて確信しました。 これからの不動産事業は、個人の根性論で現場を回すのではなく、「データ」と「仕組み」で戦うプロフェッショナルの領域になっていくと。
私たちは今、現場のオペレーションを徹底的に自動化・省力化し、人間が「人にしかできない判断」に集中できる体制を構築しています。いわゆる「時間的なゆとり」と「経済的な成果」の両立です。
そして、その先に見据えているのは、単なる民泊運営会社ではありません。 現在はまだ準備段階ですが、将来的には他社資本もお預かりしながら、より規模の大きな不動産開発・再生を手掛ける「デベロッパー事業」JpnAssetへの参入を計画し、虎視眈々と仕込みを行っています。
市場の32%は来年の拡大を計画しているそうで、競争は激化します。 しかし、私たちは焦って規模だけを追うことはしません。
まずは足元の運営を盤石にし、AIを正しく使いこなし、着実に次のステージへ上がるための「土台」を固める。 2026年に向けて、今は静かに、しかし着実に準備を進めていきます。