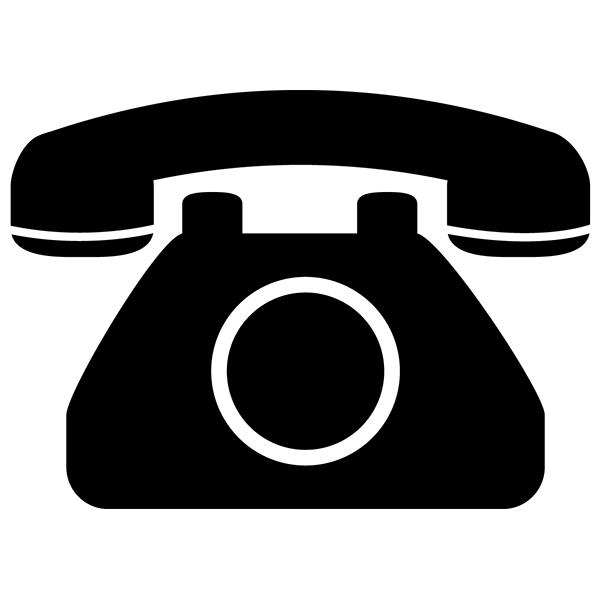仲介手数料2%・スピード重視の売却支援・スタッフも不動産オーナー



下記の物件を仲介手数料2%でご案内します
(例:1億円で売買が成約した場合、
他社であれば306万円+消費税(10,000万円×3%+6万円)となるところ
当社であれば206万円+消費税(10,000万円×2%+6万円)とお得です。)
他社であれば306万円+消費税(10,000万円×3%+6万円)となるところ
当社であれば206万円+消費税(10,000万円×2%+6万円)とお得です。)
※400万円以下は法律上の上限に従い承ります
7月18日日報 金利上昇で不動産価格はどうなる?これから起きる「二極化」の本質と、私達の戦略。
こんにちは、日本不動産株式会社の宇野です。
昨今、金融政策の正常化に向けた動きが本格化し、「金利のある世界」が現実のものとなりつつあります。この変化は、私たちの生活や経済に様々な影響を与えますが、特に不動産業界に身を置く者として、その価格動向を注視しています。
本日は、「金利が上昇すると、日本の不動産価格はどうなるのか?」というテーマについて、私の見解をお話ししたいと思います。
結論から申し上げると、私は今後、不動産市場における**「二極化」がこれまで以上に激しくなる**と考えています。
1. なぜ金利が上がると、中古不動産価格は下がるのか?
まず基本原則として、金利が上昇すると、投資家はより高い利回りを不動産に求めるようになります。銀行から借りるローンの金利が上がるため、それを上回る収益性がなければ投資が成り立たないからです。
利回りを高くするためには、家賃を上げるか、物件価格を下げるしかありません。家賃を急に上げるのは難しいため、結果として中古物件には価格下落の圧力がかかります。
2. 新築は「高く」、中古は「安く」なる矛盾
一方で、新築物件はどうでしょうか。金利上昇は、建設会社の借入コストや資材コストの上昇にも繋がります。そのため、新築物件の価格はむしろ高止まりし、利回りは低いままという状況が生まれます。
ここに、一つ目の二極化、すなわち「価格と利回りの二極化」が生じます。
3. 最も影響を受ける「築浅・築中年の物件」
この状況で、私が特に価格下落幅が大きくなると見ているのが、新築でもなく、価格が下がりきった築古でもない、**「耐用年数がまだ残っている、築浅〜築中年の中古物件」**です。
これらの物件は、「高騰する新築」との比較では割安に見えますが、「利回りを求める投資家」からは価格がまだ高いと判断され、買い手が見つかりにくくなります。結果、需給の歪みが生まれ、これまで以上に価格調整を迫られる可能性が高いのです。
4. エリアの二極化もさらに加速する
そして、もう一つの重要な視点が「人口動態」です。 日本全体で人口減少が進む中、不動産の価値は「立地」によってさらに厳しく選別されます。
山間部から平野部に人が集まるのと同じロジックで、不動産においても人が集まり続ける都市部やその周辺エリアはある程度の資産価値が保たれる一方、人口流出が続くエリアの下落は、もはや誰も止められないレベルで進むでしょう。
結論:この変化を、私たちは「チャンス」と捉える
ここまでお話しすると、不動産市場の将来に不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、私たち日本不動産は、この大きな変化を**絶好の「チャンス」**だと捉えています。
なぜなら、私たちの強みは**「中古物件の再生による価値創造」**にあるからです。
価格の下落圧力が強まる市場だからこそ、私たちの専門知識を活かして、本来価値のある優良な中古物件を適正価格で見極めることができます。そして、人が集まるエリアに絞って仕入れた物件に、リノベーションという付加価値を与えることで、市場環境に左右されない高い収益性を生み出す。
これからの時代は、まさに私たちのビジネスモデルが真価を発揮する時代です。 市場の変化を冷静に見極め、本質的な価値を持つ不動産を提供し続けること。それが、お客様と私たちの双方にとって、最も確実な戦略だと確信しています。
7月2日日報 やらない理由はない。ふるさと納税への挑戦
本日、ふるさと納税サイト「ふるなび」のご担当者様と、とお話する機会がありました。
ご提案いただいたのは、箱根町へのふるさと納税の返礼品として、当社の宿泊施設(A-frame箱根強羅、和箱根強羅)をご利用いただけるようにするという、非常に興味深い取り組みです。
もちろん、新しい取り組みには多角的な検討が不可欠です。そこで早速、経営的な観点から今回の「ふるさと納税連携」というご提案がもたらす戦略的価値について冷静に分析してみました。
【メリット】
新規顧客層の開拓: ふるさと納税に関心を持つ、納税意識や可処分所得が比較的高い層へアプローチできます。これは、まだ当社をご存じない新たな顧客層に、私たちの施設の魅力を知っていただく絶好の機会です。
集客チャネルの多様化: 現在の宿泊事業の集客はOTA(Online Travel Agent)が中心です。ふるさと納税という新たなチャネルを加えることで、特定プラットフォームへの依存度を下げ、マーケティング上のリスクを効果的に分散できます。
地域貢献によるブランド価値向上: 当社の企業理念は「『住』と『旅』を通じて、人々の幸福と地域社会の発展に貢献する」ことです。この取り組みは、箱根という地域に人を呼び、納税を通じて直接的に地域へ貢献する活動であり、まさに理念を具現化するものです。
【懸念点】
オペレーションの複雑化: 新たな予約管理や、ふるさと納税特有の精算フローを構築する必要があります。現在のリソースで対応するための仕組みづくりが課題となります。
【結論】
上記のメリットと懸念点を天秤にかけた結果、懸念点は社内のオペレーションを標準化・効率化していくことで十分カバー可能であり、それ以上に享受できる戦略的メリットが圧倒的に大きいと判断いたしました。
特に、今後の当社の成長ドライバーと位置付ける「宿泊事業」の展開を加速させる上で、極めて有効な一手になると確信しています。
このお話は前向きに推進させていただく所存です。まだ検討段階ではございますが、企業の成長に繋がる挑戦を続けてまいります。 進捗があり次第、またこちらでご報告させていただきます。
6月26日日報 夏の働き方。事業計画を前倒しで進める理由
こんにちは、日本不動産の宇野です。
本日も複数の物件立ち合いで外を走り回っておりましたが、夏の気配を肌で感じる厳しい湿度でした。少し歩いただけで汗が噴き出すこの感覚、いよいよこの季節が来たなと実感します。
毎年この時期に思うことですが、私は「夏本番を迎える前に、屋外業務は極力終わらせておく」ことを強く意識しています。
これは単に暑いのが苦手だから、というだけではありません(笑)。猛暑下での作業は、熱中症などの健康リスクはもちろん、集中力の低下による作業品質の悪化や、効率ダウンに直結します。これは経営的な視点で見ても大きな損失です。当然と言えば当然
お客様への価値提供を最大化し、共に働くスタッフの安全と健康を守るためにも、計画的にタスクを前倒ししていく。この時期の汗だくの毎日は、いわば快適な夏を迎えるための「仕込み」の期間ともいえます。
当社は賃貸だけでなく、宿泊やマンスリー事業も展開していますが、どの事業においてもこの「計画性」を大切に、質の高いサービスを提供してまいります。
6月17日 日報 あえて土地を狭くした方が得になる。
先日、土地の測量に関して専門家と協議する機会がありました。その結果、一般的には不利とされる「土地の面積を小さくする」という決断を下しました。
今回は、なぜそのような一見すると「損」な選択が、結果的に「得」になったのか、その理由を2つのポイントに整理して記録しておきたいと思います。
課題:按分比例で分けると、将来の不利益が発生する可能性
測量の結果、土地を法律に則って按分比例で分割すると、以下の2つの問題点が発生することが判明しました。
隣地の建物による「越境」の発生 按分通りに境界線を設定すると、隣地の建物の一部がこちらの土地に侵入する、いわゆる「越境」状態となってしまいます。越境物のある土地は、将来の売買時に敬遠されたり、住宅ローンの審査で不利になったりするケースがあり、資産価値の観点から望ましくありません。
境界線が建物を貫通し、不明確になる 境界線が建物の中心付近を通過する案となっており、物理的に境界がどこにあるのか極めて分かりにくい状態でした。これは、将来的な管理や認識のズレによるトラブルを招くリスクをはらんでいます。
解決策:あえて土地を2平米小さくし、問題を根本から断つ
上記の課題を解決するため、私たちは「土地を理想の面積まで広げる」という当初の考えを捨て、「問題の起きない境界線まで土地を狭める」という逆転の発想でアプローチすることにしました。
具体的には、土地の面積を約2平米小さくすることで、
隣地建物の越境を完全に解消する
境界線を建物の外壁などに沿わせ、誰が見ても明確にする
この2点を実現し、将来にわたる憂いをなくすことを優先しました。
結論:土地の価値は「面積」という量だけでなく「質」で決まる
今回の件で学んだのは、土地の資産価値は、単純な面積(量)だけで決まるものではないということです。
権利関係がクリーンであること
境界が明確であること
将来的な紛争リスクが低いこと
こうした「質」の高さが、不動産の価値を長期的に維持、向上させる上で極めて重要になります。目先の利益にとらわれず、本質的な価値を見極めることの重要性を再認識する、貴重な経験となりました。
6月3日 日報 ダブルチェックをすり抜ける。
清掃漏れが発生してまいました。
2日間にわけて、2社に依頼しているのですが、両方とも実施せず帰るというよくわからない事態。
何を考えたらそうなるのか。
今回みたいな自体を防ぐために2重の清掃費を支払っているのですが訳がわかりません。
「次世代育成支援対策推進法」及び「女性活躍推進法」に基づき「一般事業主行動計画」を策定しましたので公表いたします。
次世代育成支援対策推進法とは
次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくることを目的として、2003年に制定された法律です。国、地方公共団体、事業主、国民の責務を明らかにし、それぞれの立場で計画的かつ集中的に次世代育成支援対策に取り組むことが求められています。
一般事業主行動計画とは
企業が、子育てをしている労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者も含めた多様な労働条件の整備などを行うため、または、女性労働者の活躍推進の取り組みを着実に前進させるために策定する計画です。
https://docs.google.com/document/d/18VqgtIEjSKXVNSYDw12J1Fr9Sm4bX7zW5_dJzDyW87E/edit?usp=drive_link
女性活躍推進法とは
女性が職業生活において、その希望に応じて十分に活躍できる環境を整備することを目的として、2015年に制定された法律です。国、地方公共団体、一般事業主それぞれ責務を定め雇用している、または雇用しようとする女性労働者に対する活躍の推進に関する取組を実施することが求められています。
https://docs.google.com/document/d/1RomDoB8g_2-s3rlvSDxP683ktIT_KKJrSSINQV67JoA/edit?usp=drive_link
5月1日 日報 収容人数はどこまで影響あるか。
今日は現在運用しているのについて更なる収益アップのためにいろいろ思考を巡らせていました。
よくあるアイディアとしてはを設置することサウナを設置すること。
もう一つは収容人数を増すために宿泊棟を加える事です。
サウナを設置するのが比較的簡単な話ではあるのですが、価格に対しての影響が正直よく分からないというのが本音の話です。
収容人数を増やすというアイディアもあるんですがこれは別の宿で13名まで泊まれるよという宿しているんですけれども実際くるのは4から6人ぐらいがアッパーということもあってあまり現実的ではないような印象を持っています。
結局収容人数とかサウナとか複合的要因で結果が出てくるからどれか一つでという結論を出そうとするのがもともと間違っているという考え方になるのが正しいでしょうけど、なんかしら結論を出さないといけない立場としてはちょっとこれだと寂しい。
あとは価格感度とか設定についてどの程度のアップ効果があるかという分析もできないのでどこまで費用対効果そして投下する価値があるかというのが考えられないこれもネックではあります。
ということで明確に数値化しづらい案件についてどのように取り組むかというのを悩んだという一日でした
4月14日 日報 エクセルと格闘
今日は顧客データと入居や物件の稼働日数に対してどの程度稼働しているかというためのガンチャートに近しい表を一生懸命作ってみました。
どのようになったかというとGoogleのスプレッドシートに対して、タイムラインという機能があるのですがこれを利用すると日付別に横軸に自動的に入力されます。
データベースを書き換えるとさらに行数が増えていくのでタスクリストなどをいろいろ入れて行くとうまい具合にガンチャート式で表示されるようになりました。
トータルでは一時間半くらいかかっていて最初の簡単な部分はすぐ来たのですが、表示したくない所とか必要のない情報部分を限定して表示させるっていうところに対していろいろ関数を組むのに苦労していたところ。あとは並べ替えがうまく表示されていなかったのでどうやったらうまく表示されるかなということをいろいろ悩んでいました。
その辺も自分に対してどうやったらいいかを質問しながらやったら割と早くできました。
もしこれ全部自分で書いているともっともっと時間かかっていると思います。
これで外部のプログラムお月額数千円で導入しようかと言って色々悩んでいたところがだいぶ解消されました。
生成AIやスプレッドシートなどの進化は本当に速いのでついていけるように頑張りたいと思います。
4月5日日報 新しい流動性商品
インターネットの会社さんとお話ししていて債券を流動化してそれを投資家に販売することによって資金調達を行う。その利用者はその分の代金をこのインターネットの会社に支払うという方式の商品説明を受けてきました。
金利手数料自体が高いんですけれども、いや厳密には金利ではないので金利という表現は正しくないですね。利用手数料と言った方が良いでしょうか。
まあとは言え正確な言葉遣いと言うよりもみんなに理解してもらう方がいいと思うのでいいので手数料は今回金利として表現しますが大金利手数料としては5%から8%程度でしょうか。
それである程度融通効かせた資金調達ができるということなのでこれはかなり使い勝手がいい。
期間は最大10年
物件購入費用としては使えないんですけども建築費用やリフォーム費用としては使えるので場合によっては新築の方が晴れがいいというパターンです
ひとまずはあまり深く考えずにその場ほんと理解することだけにフォーカスしていたのですが、帰ってきて落ち着いて考えてみると結構えげつないなと。これはいい意味でです。
ということで何ができるか色々整理して新しく仕掛けていきたいと思います
4月4日日報 これからの採用の主流を考える
先日はスポットバイトの会社さんと打ち合わせしました。
内容はスポットバイト利用しませんか。またそこから長期採用につなげませんか。という話です。
これだけだと大した話に聞こえないかもしれませんが、これまで大きく変わってくるなと感じるところとしましては採用面接の先に業務を実際に体験するというのが先行するというところがこれまでと大きく変わるところです。
つまるところ働く人としてもどんな職場なのかよくわからない、雇用する側から見てもどんな人かよくわからないというままで仕事してないと分からないということは多々あるかと思います。
その中でスポットバイトとして何回か来てもらうことによってどんな人がある程度分かった上で雇用に繋げると。
1回働くなると短くて2 3時間長くて5時間から8時間ぐらいでしょうか。
まあそれだけ働くと採用面接30分するよりよっぽど長い時間いるわけですからどんな人かというのも大なり小なりに見えて来るというもの。
言うならば30分面接じゃなくて5時間から8時間の長期面接と考えてもいいかもしれません。
長期面接という視点で行けば30分より8時間の方がより見抜くには適しているでしょう。
ということで今後はこのような形式の採用プロセスが増えていくのではないかというところで感じた一日でした